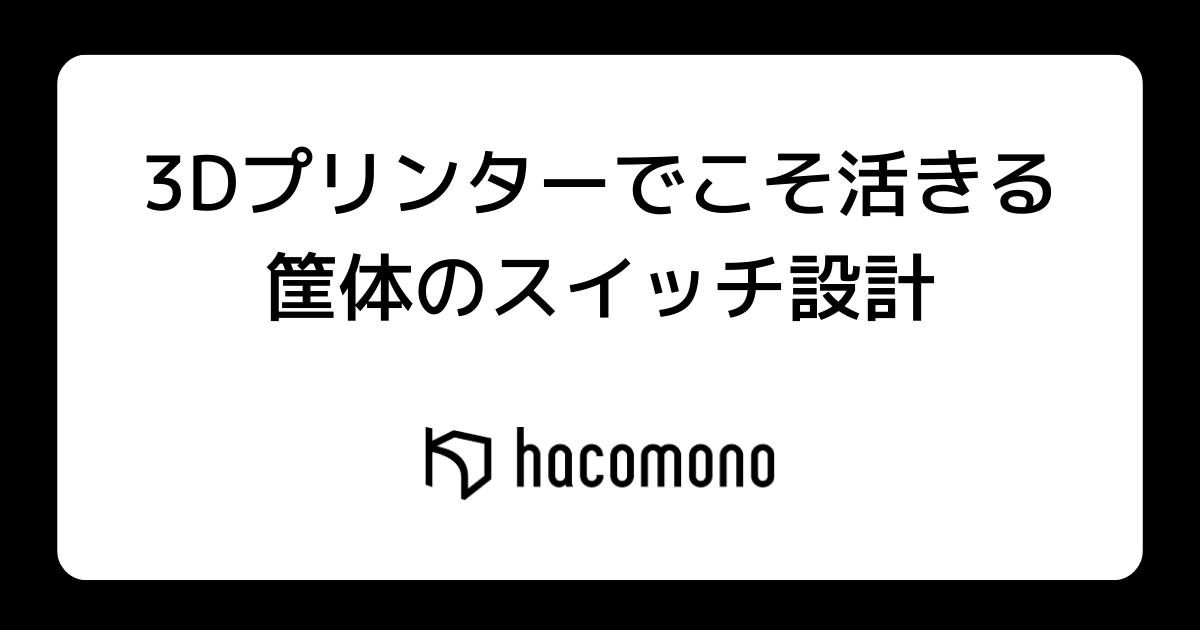 こんにちは。ハードウエアのメカニカルエンジニアデザイナーをやっている うら(Ura)です。
こんにちは。ハードウエアのメカニカルエンジニアデザイナーをやっている うら(Ura)です。
メインプロダクトがSaaSということもあり、ソフトウエアプロダクト中心の弊社ですが、実はハードウエア領域でも自社プロダクトを開発しており、メーカーという一面もあったりします。
PCBA(Print Circuit Board Assembly)から筐体の金型設計、SCMからデリバリーまで、実は社内でかなりの部分をコントロールできる体制を作っております。
型だと絶対に不可能で3Dプリンターならではのおいしいスイッチ
長くなりそうなので結論からずばり言っちゃうと
「サイドアクセス型タクトスイッチの押し子パーツの筐体との一体成型構造って、いくつかやり方ある中でも、設計自由度が高くてオシャレでかつ3Dプリンターならではの構造をプロトでよく使います」という記事になります。
何言ってんの??という方のために以下解説。
メカ屋はモノの成り立ちを考える
メカ屋の仕事とは極論、かたちx材質x作り方 が全てと言っても過言ではありません。それぞれの要素についてどれだけ深い知見があるかがメカ屋の基本的な素養とも言えます。リアルのモノというのは形状特性とか材質特性とかもさることながら、その製造技術、どうやってモノを作り出すか?によっても必要な設計要件が変わってきます。
- プラスチック筐体を量産する場合は金型で作るので、型で成型できる前提の設計データが必要
- 板金で筐体を量産する場合はプレス型で打ち抜くので、打ち抜ける前提の設計データが必要
みたいな感じです。
それができていないと物理的に成り立たない設計、絵に描いた餅となって、工場にめちゃくちゃ怒られちゃいますし、社内的にも怒られちゃいます。
成り立たない設計を回避するには、設計のフロントローディングやフィジビリティをしっかりやること、さらには断面(Section)で考えることが重要と先輩設計者の皆さんから教わって私は育ちました。
CADによってはSectionなんて切らないCADもあって、私なんかはめちゃくちゃ事故ってそうで恐いんですが、最近のトレンドはそんなこともないみたいで、このあたり育った企業文化によって同じメカ屋でも考え方や文化が違うところですね。
金型には「型を抜くのに必要な抜きテーパー」というものが存在します。

金属ブロックに彫った空洞に溶けたプラを流して固めたあと、型を開いて製品を取り出すわけですが、型が開くのを製品形状が阻害してしまうと壊れた製品しか取り出せず、ひどい場合は型そのものも壊れます。

このような型開き阻害形状をアンダーカットと呼ぶのですが、アンダーカットは設計者も血眼で確認しますし、製造側でも金型を起こす前に必ずチェックが入ります。
3Dプリンターは直接樹脂を積層していくのでそもそも型がないですし、そのような生産上の制約がもっとゆるいです。アンダーがあろうがなかろうが積み重ねることさえできれば大抵は物理的に成り立っちゃうわけです。
そんなメーカーズムーブメントで盛り上がりを見せた3Dプリンター品もそれはそれでネガがもちろんあります。フィラメントや光造形や粉体造形など手法は色々あるにせよ、母材となる材質を積層していくので積層痕や積層界面の影響を考えないといけないですし、プリンター品をそのまま量産適用しようと思うと生産タクトタイムが長すぎて(型物1ショット:~数分に対して、3Dプリンター:数時間~数十時間)よっぽど上手くやらないとなかなか量産コストで型物品に勝てないため、実際の製品への反映と考えるとまだまだハードルが高いように感じます。(イニシャルはひとまず置いておいて)
そのためプリンター品は一品物や試作ソリューションとして弊社でもよく登場します。私が新卒の頃の試作と言えば粉体造形か切削かでしたが、近年はプリンター試作もずいぶん増えましたし、そのようなサービスを提供して下さる企業も増えましたね。
・・・と言った具合に、ハードのメカ設計者はモノ自体が好きなこともさることながら、ある程度基礎的な物理に立脚した製造技術マニアである必要があります。youtubeでつい工場の動画を見ちゃう人や、工場萌えする人、製品を分解してリバースしちゃう人なんかは実に向いている職能ですね。
メカ屋視点のスイッチ

ハードウエアデバイスはソフトウエアによる制御の他に、ハードウエア側(ユーザー側)での制御が発生することがあります。
ハードウエアデバイスのモードを切り替えたい
ハードウエアリセットをかけたい・・・とかとか。
エレキとしては基板の上にタクトスイッチなんかを実装してそれを実現しますが、ちゃんと体裁を整えてある製品、つまり基板単体で販売するわけではない筐体にアセンブリされた状態で市場に出ていくような製品は、当然筐体の外からスイッチにアクセスできる必要があります。
- 防水にしたいけど穴が空いていたら水入ってきちゃうよね?どうやってスイッチ押す?
- スイッチ押せるようにしたいけど部品点数は増やしたくないよね?何とか減らせない?
- スイッチのクリック感のフィーリングを良くしたい、軽くしたい、重くしたい。
- 仰々しいスイッチはブランドイメージにそぐわないし、もっとオシャレにしたいんだけど?
などなどのユーザービリティ要件やデザイン要件、もちろんメカやエレキとしての要件なんかを踏まえてエレキのエンジニアとあーでもないこーでもないと最適な仕様をつくって、かつ生技性や信頼性も含めて実製品として実装していきます。こういう所がメカ屋の腕の見せどころになってくるわけですね。
・・・前置きが超長くなりましたがここまでがインプットしてもらいたい前提知識で、今回のテーマはその中でも3Dプリンターで面白い構造が実現できたのでそのご紹介となります。
こんなスイッチ構造

ポイントとなるのは積層を信じてあえてどアンダーを作るという構造です。
青いエリア:今回スイッチの押し子を設計した筐体のボトムケース
緑のエリア:相手部品となる筐体トップケース
オレンジのエリア:PCBAとサイドアクセスのタクトスイッチ
- 反発の金属バネを必要としない。RIB板厚の反発を利用して押し子を戻している。スイッチストロークは一般的なタクトスイッチで0.1mm近辺なので、あえてバネを設ける必要がない。板厚たわみが効かせられる高さのRIBさえ設置できれば設置可能。
- 押し子を一体成型することができる。部品点数が減らせるためスイッチ押し子部品を別体で設計したり、アセンブリ工数を確保する必要がない。
- 基板位置のレイアウトに柔軟性を持たせることが可能。筐体から奥まった位置にスイッチが来てもスイッチ押し子の方で調整がいくらでも効く。壁際にレイアウトするために頭を悩ませる必要がない。
- 試作でもある程度見栄えの良い物理ボタンなので、プロトとしてイメージを伝える時に説得力があるデザインを作りやすい。
このやり方ですとスイッチ下部のエリアは根こそぎアンダーとなり、通常の金型では物理的に型抜きが不可能ですし、軽微なアンダーを抜くためのスライド機構も入らないため、金型では完全に実現不可能です。3Dプリンターはこんな無茶な形状も物理的に成り立ってしまうのでそこを逆手にとっている設計です。

注意点としては
- たわみRIBの長さをできるだけ長く確保して樹脂材の弾性限界を超えないようにすること
- たわみRIBとケースの肉裏の間にサポート材の悪影響を回避できる程度のスペースを確保すること
- 押し子がRIB根本を中心にほぼ回転軌跡で動くので回転クリアランスが取れるクリアランス設定を考えること
- 金型で量産しようと思ったらもちろん成り立たないので、成り立つ設計に修正するのを忘れないこと
などが挙げられます。モノとしては下の写真の筐体のような外観になります。

3Dプリンターの特性、材質の特性、形状の特性を十分に活かしてコスパ良く設計することで、自分も楽になりますし、なにより設計すること自体が、モノを生み出すこと自体が、どんどん面白くなっていきます。
まとめ
昔誰かが言っていました。工業化とは標準化の歴史であり、工業製品は「貧富の格差をフラットに慣らすためのツール」であると。
貴族の乗り物だった自動車が民衆まで広がって同じファンクションを享受できているように、大金持ちが腕に巻いているのがAppleWatchであるように。その工業製品はどれだけの数が出たか?は、成し得た標準化の成果でもあります。数こそが絶対的な正義でありプロダクトの存在意義そのものです。
インダストリアルデザインは量産も見据えてモノの仕様を作るので、様々なものが生産数の分だけ掛け算です。特にメカの世界は選択肢があまりにも多く変数が複雑に絡み合った世界です。
1円でも安く、1gでも軽く、1mmでも小さく、常にコストとの戦いですが、安価で見栄えの良い仕様が組めた時などは、うまくできた!と感動できる仕事でもありますし、出荷数の分だけ助かる人がいると考えると小さい仕事でも大きなレバレッジがかかる、影響力の大きいエキサイティングな仕事です。
パテントや実用新案、R&Dやノウハウなど、やや政治の世界もありますが、本当はメカ屋だってソフト屋さんのように共有知を増やして行きたいと思っている同業の方も多いと思います。私もその一人です。
今回テックブログを書くにあたりテーマは非常に悩みましたが、知見の広さや経験値の豊富さがエンジニアが出来ることを増やしてくれる、ひいてはこの世界の富がちょっと増えることを期待して、プロトタイプでよく使うテクニックのひとつをご紹介しました。
当記事の執筆者が所属するIoTチームの記事も是非ご覧ください!
株式会社hacomonoでは一緒に働く仲間を募集しています!
採用情報や採用ウィッシュリストも是非ご覧ください!